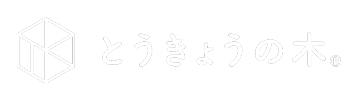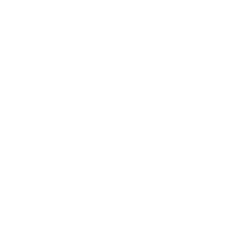高層ビルが立ち並ぶ新宿からほど近い代々木公園や明治神宮がある地域は、緑豊かで静かな住宅街が広がっています。そこに小田急線の参宮橋駅があります。周辺住民や代々木公園などを訪れる人が利用する、小さな駅です。この駅は2020年に改装され、非常に洗練されながらも、親しみあるデザインに生まれ変わりました。そこで選ばれたのがとうきょうの木®。長年地元に愛されてきた駅の改良工事に際して、どのようなことが考えられ、地元の方々とどのような交流があったのでしょうか。
小田急電鉄㈱工務部の糟谷拓海(かすやたくみ)さんにお話を伺いました。

工務部の糟谷拓海さん
- 先般、参宮橋駅に伺わせていただいて、多くのとうきょうの木®を使っていらっしゃることに、驚きました。また都心なのか?と思うくらい、くつろげるようないい雰囲気だなと感じました。糟谷さんは、参宮橋駅の工事の時はまだ入社なさって間もない頃だったと思いますが、その頃は、どのような印象でした?
- 糟谷さん参宮橋駅は明治神宮が近いので、すごくゆったり時間が流れている雰囲気がありますね。私はたまたまなんですが、子どもの頃から付近の国立オリンピック記念青少年総合センターの体育館などに、よく行ってました。都心部なんだけど、近隣の代々木上原や新宿のような雑踏がなく、落ち着いた感じの雰囲気で、すごく魅力的だなと感じていました。入社した時にちょうど参宮橋駅の改良工事の話があって、当時他の業務に従事していた私も横目で見ていたんですけど、木材を多く使っていて街の雰囲気に合うなと感じていました。

- 駅で木材を使うということは、鉄道の世界では結構大変なことなんですか?
- 糟谷さんやっぱり電車を動かしているので、「落下する恐れがあるもの」をあまり使いたくないんですよ。木材はどうしても朽ちていく。駅舎で使うには、どの木材をどこに使うかしっかりと見極め、接合部分の施工も工夫すること、しっかりとメンテナンスし続けられることなどの条件を整える必要があるので、木材を使うことはハードルが高いんです。参宮橋駅では、そういう条件も考慮しながら、「近隣の街並みに調和する雰囲気は大切にしたいよね」という思いがあって、木材を使いましたね。

- それは近隣の街並みとの融合ということから、とうきょうの木®を活用するということだったのですね。
- 糟谷さんそうですね。周辺の雰囲気に合わせて木材を使いたいのはもちろんあったんですけど、小田急電鉄が環境戦略として木材など資源循環に取り組んでいることも、理由です。間伐材も含めて地場産材をしっかり使うことで、沿線の木材産業に貢献していくということが、企業としても重要だと考えています。
また、我々は鉄道会社として「交通結節点」を提供しているので、多くの人が滞留する空間で木材を使うことで、お客さまやお子さまに木に触れていただける、香りを感じていただける。多くの方に「木」に対する興味を持っていただく機会を提供できたら、うれしいですね。

- 周りの雰囲気との融合というところでは明治神宮ですね。都心の森が背景にあることは、意識されていますか。
- 糟谷さんありましたね。背景に緑豊かなエリアがあり、裏参道と呼ばれる明治神宮への道があって、樹齢300年以上の古い木や大きな木もあります。地域の人にとって木というものがかなり重要視されていると感じます。木に対する意識は他の地域よりもやはり高いのではないでしょうか。

- 参宮橋駅近隣地域の方々と、どのようなやり取りをなさったのか、当時工事に携わられた方からお聞きになっていますか。
- 糟谷さん古い駅舎の改札前に古木がありました。移植が難しいほど腐朽しており、改良工事に伴ってそれを伐らざるを得なかったんです。木への意識が高い地域で長年親しまれていた木ということもあり、地域の方々に配慮が必要でした。そこで、近隣神社の宮司さんにお願いしてお別れの式を実施し、その端材を地域の希望する方にお渡したんです。
工事に対する理解と、我々が地域の方々と一緒になって、木を大切にしながら次の世代に繋げていくことに共感してもらえるように行った取り組みでした。なかなか、このような機会は当社でも少ないことだったのですが、参宮橋駅を使い続けてもらうには、地域との関わり合いっていうのが大事だということを当時の担当者から聞いたのが印象に残っています。

- 逆に地域住民の方から、完成後の感想や、お声掛けっていうのはありましたか。
- 糟谷さん当時の担当者に聞くと、やっぱりできた当時は、「これって何を使ってるの?」とか「キレイになったね」って、お声掛けをいただいたっていう話は聞きました。また、参宮橋駅を利用してくださっている、近隣の大学の先生に興味を持っていただき、駅見学授業を開催するなど、地域連携のきっかけになっています。

このように、小田急電鉄の森林循環や地域に対する、企業の思想や強い思いが形になったのが、参宮橋駅なのでしょうか。新しく生まれ変わった参宮橋駅は、都心の駅で感じられる慌ただしさや、喧噪はなく、ご利用されている方々も、ゆったりとした印象です。駅の屋根部分には古来の建物にみられるような、端を斜めに裁断した部材や、格子状に木を組んだ構造の意匠が多くあります。またホーム上の駅の銘板が全ての柱にあって、沢山の玉垣が奉納されている神社のようにも感じられます。
このような細部にまで工夫されているデザインが、周囲の環境や利用される人たちの心を動かしているのではないでしょうか?先ほどお話にあがった近隣の大学で教鞭をとられている、文化学園大学の丸茂みゆき教授にもお話を伺いました。
- 東京で育ち、伐採された木とうきょうの木®を利用した参宮橋駅ですが、生活者が木材、とうきょうの木®を使う良さはどこにあるのでしょうか。
- 丸茂教授大学から歩いて10分と少しで駅に着きます。駅前の坂道の途中にある西口改札は、上部に組まれた木材に光があたり入る人を迎えてくれます。木漏れ日の下を歩いているような気分ですね。下りホームの間接照明で木が綺麗に見える様子は、急行などで通過している人が「あれ?」と思っているかもしれません。新宿駅から各駅停車で2駅とは思えないゆったりとした時間が流れている場所だなといつも感じています。それがとうきょうの木®でつくられているのは誇らしいですね。

- 参宮橋駅のようにとうきょうの木®に、東京の生活者が触れることができる施設についてのご意見をお聞かせください。
- 丸茂教授都心では人工物に囲まれた生活をしています。ですから木材が時間と共に変わっていく様を気持ちよく美しいと思えるようになりたいですね。地元の木を使うことは特別な事ではなく「日常」と感じて欲しい。自分が使うことで森が大事にされ、そのことで自分自身が守られる感覚になっていきたいです。
私は2010年からとうきょうの木®を使ったインテリア小物や家具を制作する授業を行っていますが、学生にも同じように伝えているつもりです。授業では木の香りや柔らかさ、そして美しさを感じて気持ちよく作業が出来ています。参宮橋駅に行くことは(木の香り、柔らかさ、美しさを)空間体感が出来る良い機会になっています。

このように、駅など生活者の日常に寄り添う空間でとうきょうの木®が使われることが、森林循環を促していくと同時に、都心でくらす人たちにもとうきょうの木®を通じて多摩地域の森林を感じていただく場であることがわかりました。小田急電鉄の糟谷さんは、最後に「駅に木材を使うという機会があれば是非チャレンジしたい。とうきょうの木®に関心を持って、一緒にチャレンジする仲間が増えると嬉しいですね。」と仰っていました。とうきょうの木®には、様々な利用の可能性があります。様々なデザインによって、新しい価値を訴えることもできます。是非みなさんも、とうきょうの木®を使って、森林循環を未来につなげていきませんか。