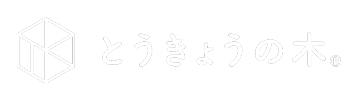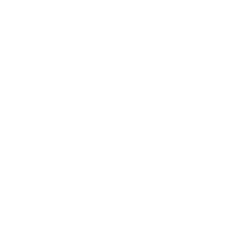10月24日(金)~10月26日(日)に東京味わいフェスタ2025が都内の4会場で開催されました。その中の豊洲会場は「東京の豊かな農林水産業を体験できるエリア」で、とうきょうの木®もブースを出店し、ブランドをアピールしました。
また、10月25日(土)に、ステージで手回しオルガンのパフォーマンスを行うKoji Koji Mohejiさんに、「とうきょうの木®とコラボレーションをしませんか?」と呼び掛け、利用事業者の木具定商店さんと試行錯誤してつくったとうきょうの木®の手回しオルガンで「とうきょうの木®スペシャル仕様」の演奏をしていただきました。
とうきょうの木®で
手回しオルガンをつくってみた
- 手回しオルガンは、私たちには馴染みのない楽器なんですけれども、どのような楽器なんでしょうか。
- Koji Koji Mohejiこの楽器は半自動演奏楽器となっていて、演奏する人によって、楽器にも機械にもなります。後ろにハンドルがついていて、回すと「ふいご」が動いて空気をリードに送り音がでます。そしてこのブックという穴の開いたカードを使って初めて演奏することができる楽器です。

- 今回、とうきょうの木®とのコラボレーションのご相談をさせていただきましたが、聞かれたときは、どんなことを考えましたか。
- Koji Koji Mohejiまずはワクワクでしかありませんでした。いろんな木材に触れてみれるチャンスというのは、なかなかないのと、もともとは東京に住んでいたこともあったので、とうきょうの木®ってあるんだなというのを初めて知って、どんな木なのかなって、ワクワクしながら興味を持ちました。

- 今回はとうきょうの木®でオリジナルのケース(音を出す機械を覆う箱)をつくって演奏していただきました。
普段はどのようなケースで演奏をされてますか? - Koji Koji Moheji普段はウォールナットとか、もっと硬い木を使ったり、捨てられてしまうような、古いアンティークの家具の木材を磨き出して使ったりしてます。

- なるほど、普段とは違う素材になったのですね。それによって、音の出方って何か変わりましたか。
- Koji Koji Mohejiそうですね。新しい木だったので、実際に音を聞いていただくとわかるんですが、水々しさが残っているような、ちょっとまろやかさがあるような音になったような気がします。

- やはり木の古い・新しいとか、針葉樹・広葉樹とか、素材の木材によって音質が変わってくるんですか。
- Koji Koji Mohejiそうですね、多少ですけども響きの具合ですとか、木目の具合とかで変わってくるのかなと思います。
また楽器を加工していく中で、新しい木というのは反ったり、柔らかいこともあるので、いつも使っている木材のマテリアルとはちょっと難しさが違いました。

今回、Koji Koji Mohejiさんには、オルガンの本体を覆う「ケース」を、とうきょうの木®でつくっていただきました。それによる演奏が、この映像です。
今でも愛される木を使って、
新しい楽器にチャレンジも
- 今日もそうだったんですけれども、お子さまたちが結構寄ってきてくれるんですが、手回しオルガンを通じて木への興味を持ってくれているんでしょうか?そんな実感はありますか?
- Koji Koji Mohejiそうですね、こういうアコースティックな楽器を作っている立場から見ると、今はプラスチックなどのいろんな資材ができてくる中で、木というのは昔からどんなに進化した新しいものができても、やっぱり変わらず残っているものですよね。たぶん今日の子供たちも近くで見て、触って音を聞いて、木の良さというのを直感的に、感じていることは、すごくあるんじゃないのかなと思っています。私はこれからも何か木でつくる上では、違う木材も試してみたいなと思っています。木の良さを引き出せるようにはしていきたいなと思っています。

- この手回しオルガンのほかにも、いくつか楽器の演奏を、パフォーマンスしていらっしゃると思うんですけど、今後とうきょうの木®を使ってチャレンジしてみたいなと思われる楽器はありますか?
- Koji Koji Mohejiそうですね、今やっぱりパッと頭に浮かんだのは、2種類の手回しオルガンの音色の種類があって、今日はアコーディオンのようにリードが入っているタイプのものを使ってケースを作らせていただいたんですが、もう一種類のパイプオルガンのような、フルートタイプって言われているタイプのオルガンです。音の鳴るもとから木で作ることができるので、よりこの木の影響をすごく音が受けやすいので、それで作ってみたいなと思いました。
会場にいらした、小さなお子さまを連れた家族の来場者の方々も、非常に楽しそう。30分間のステージを、充分楽しんでいただいたようです。

今回、手回しオルガンで使われた「ケース」には、とうきょうの木®のスギを使ってもらいました。このように、とうきょうの木®は、様々な使い方ができます。このイベントでは、とうきょうの木®のお箸と箸置きを、来場されたみなさんとつくりました。この他にもとうきょうの木®を使って、DIYで家具やアクセサリーをつくることもできます。多くのみなさんに、とうきょうの木®を知ってもらい、様々な使い方を考えてもらうことで、とうきょうの木®の新しい用途や商品が増えていきます。このように都民のみなさんと、とうきょうの木®の商品をつくっていくことができればいいですね。