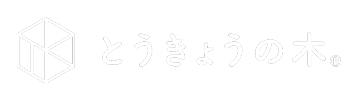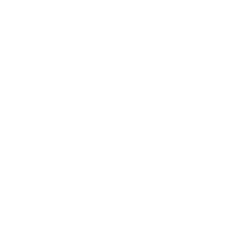とうきょうの木®を生活に取り入れ、豊かで健やかなくらしをしながら、多摩地域の森林の持続化も意識しているという秋本ご夫妻の、お宅に伺いました。とうきょうの木®に囲まれた、ライフスタイルに関するお話や、地元である多摩の森林への思いなどのお話をお聞きすることができました。
とうきょうの木®を
知ったきっかけは?
私たち夫婦は建築家として、木造住宅をもっと知りたくて東京都民の森で森林ボランティアに参加しました。そのとき、東京には木がたくさんあるのに使われていない現状を知って、「いつか自分たちの設計でも使いたい」と思ったんです。でもなかなか機会がなく、実際に家を建てる話が出たのはコロナ禍の頃。それは、国産材が注目されるタイミングでした。そこで、東京都が主催するMOCTIONで、製材所と設計事務所のコラボ講演会に参加しました。「とうきょうの木®で家が建てられる」と知り、すぐに製材所を訪ねて具体的に動き出したんです。

とうきょうの木®の家に
住んでみて感想は?
建て替えるまで普通のビニルクロスを使った家に住んでましたが、木の家に住んでみて、やっぱり空気が違うって実感します。玄関に入ると 木の香り がして、家族も「落ち着くね」とよく言っています。ご近所の方や息子の友達も、「すごくいい香り!」と驚くほど。夏は 冷房を弱めでも快適 で、一日中つけっぱなしにしても温度が安定しています。冬も 晴れた日は昼間の暖房がいらないほど暖かく、普通の家とはぜんぜん違います。前日に暖房を消して寝ても、朝の目覚めが違いますね。

多摩地域の森林に対して
なにか想いは?
多摩地域の森林は、東京の森の大部分 を占めています。でも、せっかく木がたくさんあるのに、うまく活用されていないのがもどかしくて…。特にスギは花粉のせいで悪者扱いされがちですが、本当はもっと活かせるし、使えば 自然の循環 にもつながります。それに、近くの森の木を使えば 輸送コストも抑えられ、ロスも少なくなるし、エネルギー的にも効率がいい。昔は 家の裏山の木で家を建てる のが普通でした。東京でも、遠くの木を使うより 身近な木を使う ほうが環境にもなじみやすく、家にも自然とフィットするんじゃないかと思います。

最後にみなさんへ
メッセージを
自分たちが家を建てるときに、とうきょうの木® を使う選択肢を一度考えてみてほしいです。自分たちが住んでいる 身近な森の木を使うことで、エネルギーの無駄を減らし、本当のエコ活動になると思います。実際に奥多摩に行くと、森が荒れてきているところもあります。森林循環がうまく回っていない現状が、垣間見えてしまうんですよね。これを改善するためには、東京に住む私たちがとうきょうの木®を使い、森の循環を支えることが大切だと思います。身近な資源を活用することで、環境にも地域にも良い影響を与えられるはずです。

とうきょうの木®で建てた家で、秋本さんご家族が快適に暮らしている様子が伝わってきました。また、この家づくりの相談を最初に受けた 沖倉製材所の沖倉善彦さんにも、お話を伺いました。
東京で使う木は
東京で育った木が一番?
とうきょうの木®を暮らしに活かすことは、究極の地産地消 です。東京都の約4割が森林で、江戸時代から林業が続き、質のいい木が育つ環境 があります。また、東京の気候で育った木は、その気候や湿度に適応しているので暮らしになじみやすいとも言えるでしょう。とうきょうの木®を東京で使えば、輸送距離が短くなりエネルギーの無駄も少なくなる。ウッドショックの際も輸入材の供給が滞る中、とうきょうの木®なら 素早く製材・運搬できています。地域の木を地域で活かすことの重要性を、改めて感じています。

とうきょうの木®で
家一軒建てることは可能?
東京の森には スギ・ヒノキ・キリ・クリ など、様々な木があります。スギやヒノキは強度が優れている ので、構造材としても十分に使えます。秋本さんのお宅は、実際にとうきょうの木®をふんだんに使用 しています。土台や柱、梁には選りすぐりのスギやヒノキを採用。床・壁・天井にも使い、フローリングはヒノキを敷いています。建具や枠材も、地元の職人さんが無垢材で仕上げたものです。外壁にもスギ材 をたっぷり使用し、耐久性の高い 赤身材 を厳選しました。限られた量の木材ではありますが、とうきょうの木®だけで家を建てることは十分に可能 です。

とうきょうの木®を使うことで、快適な暮らしが実現するだけでなく、環境負荷の低減や森林の循環にもつながります。家づくりにとどまらず、とうきょうの木®の多様な可能性を、みなさんと一緒に探っていきたいと思います。