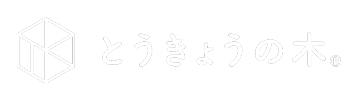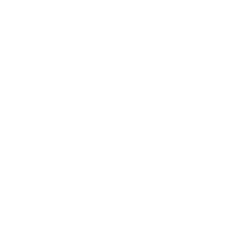今年(令和7年)の大河ドラマ『べらぼう』は、江戸時代の庶民の暮らしを描いた作品です。そこで、現代の「とうきょうの木®」だけでなく、江戸時代から続く木の活用にも目を向けます。1590年、徳川家康の江戸入府とともに町づくりが始まり、建築や水道の木製管、生活用品に至るまで木材が幅広く使われていました。江戸の人々は、森林を管理しながら木を活用し、資源を守ることの大切さを理解していたのかもしれません。そうした木との関わりは、時代を超えて受け継がれています。
木で作られた
世界最大の都市「江戸」
徳川家康が江戸に入府する以前、この地は湿地が広がり、人々が生活しにくい環境でした。しかし、家康の入府とともに本格的な町づくりが始まり、豊富にあった木材が重要な資源となりました。木は加工しやすく、建築資材として適していたため、町の発展に欠かせない存在だったのです。寺社や家屋の建築にはもちろん、江戸の水道網を整備する際にも木が使用されました。木を水道管にも使い、長距離にわたり水を運ぶために活用され、江戸の発展を支えました。こうした木材の利用は、都市の成長とともにさらに拡大し、江戸の基盤を作り上げたのです。

木材で作られた上水道「水道橋」が描かれている
資料提供:東京都立中央図書館
庶民の暮らしと
江戸の木の関わり
木は建築資材としてだけでなく、庶民の暮らしの中でも広く活用されていました。食器や家具、道具などの日用品の多くが木で作られ、木材は身近な素材として親しまれていたのです。また、木製の桶や樽、農具なども普及し、人々の生活に欠かせないものでした。江戸の人々は、木を大切に使いながら暮らしていました。木材を再利用したり、廃材を燃料として活用するなど、資源を無駄にしない工夫もなされていました。また、建物や道具の修理を繰り返しながら長く使う文化も根付いていました。江戸時代の町と暮らしは、まさに「木と共にあった」といえるでしょう。

当時の有名寿司店『深川の松ヶ鮨』を描いた。
左下に折箱が見られる。
資料提供:東京都立中央図書館
江戸時代、木は町づくりから庶民の暮らしまで幅広く活用され、資材を大切に使う文化が根付いていました。そうした江戸の木への技と想いは今も受け継がれています。今回は、天保年間創業の木具定商店・信田ご夫妻に、木具を通じた木の活用についてお話を伺いました。
御社名の「木具」とは、
何を指すのでしょうか?
木具定商店は天保時代から続く老舗で、現在の代表は6代目。木具とは、木で作られた道具や器の総称で、これを作るのが木具師(きぐし)と呼ばれる職人です。昭和に入り、多くの木具師が「〇〇折箱店」などに変わる中、初代・定吉の志を受け継ぎ、「木具定」の名を守り続けています。

主にどのようなものを
扱ってこられましたか?
木具定商店の柱は二つあります。一つは折箱、もう一つは宗教関係の御札です。折箱は、和菓子やお寿司、高級なお弁当の容器に使われ、木の香りや通気性の良さが食品を引き立てます。しかし、近年ではパック製品が主流となり、折箱の需要が減少し、出荷数も減っています。江戸時代から明治にかけて花開いた折箱文化が、衰退しつつあるのが現状です。そこで、折箱を守るため、木製ストローやモビールなどの開発にも取り組んでいます。天保時代からの伝統を守りながら、現代に合った形で木の良さを伝えていきたいですね。

折箱や経木づくりで、
難しいところは?
木材を使う上で大事なのは、水分管理です。スライスするときは水分が多いほうが加工しやすいですが、変形するので、しっかり乾燥させる必要があります。厚さが均一じゃないと仕上がりも良くなりません。節(ふし)のない柾目(まさめ)の木が適していて、木目が曲がった板目(いため)は折箱やストローには向きません。乾燥すると木が反るので、二枚合わせにすることも。結局、折箱を作るには、きちんと管理された山から切り出した上質の木を使うのが一番大事なんです。

江戸から続く折箱を通して、
森林への想いは?
木材は、地球環境への負荷を抑えながら循環利用できる資源です。「切って使い、また植える」サイクルが成り立てば、カーボンニュートラルが実現し、温暖化ガスを増やさずに利用できます。しかし、計画的な植林がなければ持続的な循環は難しいので、山の管理が非常に重要です。木の伐採は環境破壊だとよく誤解されるのですが、適切な伐採と植林を繰り返せば、環境を守ることにつながります。木は循環利用できる唯一の資源であり、そのためにも利用を促し、価値を広めることが重要です。

今回のインタビューを通じて、江戸時代から木が庶民の暮らしに深く根付いていたことが改めて分かりました。建築や生活用品に活用されるだけでなく、廃材は燃料として再利用され、木材は無駄なく使われていました。人口の増加とともに木材の需要も高まり、江戸幕府は多摩の森林を直轄地として管理し、人工林を整備。多摩の木は筏に組まれ、多摩川を下って江戸へ運ばれ、資源を守りながら有効活用する仕組みが築かれていました。時代が移り変わり東京となった今も、多摩の森林は都民の暮らしを支え続けています。木を使うことは環境を守ることにつながる。だからこそ、「とうきょうの木®」を見直し、その価値を次世代へとつなげていくことが大切だと感じました。